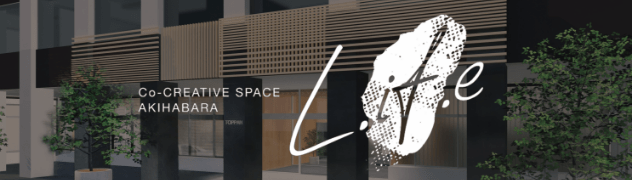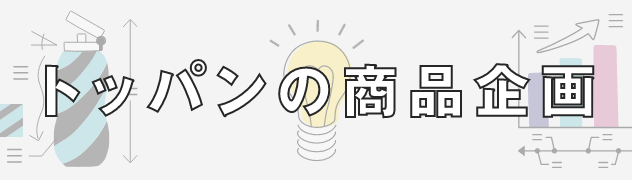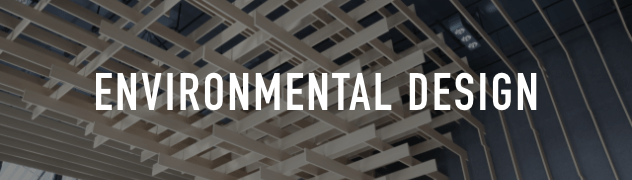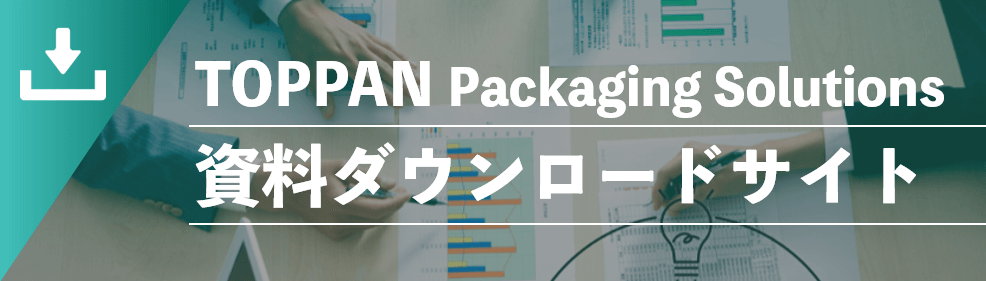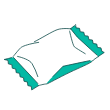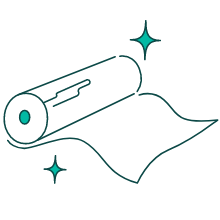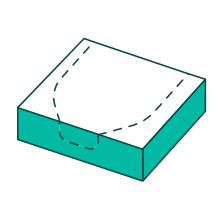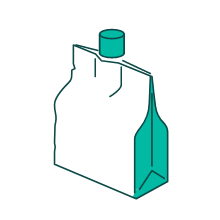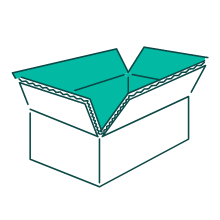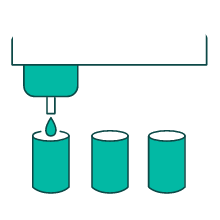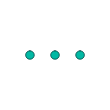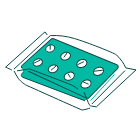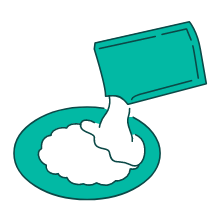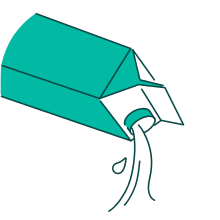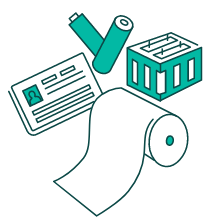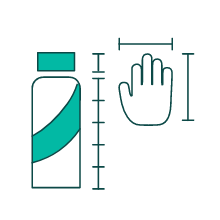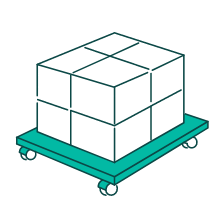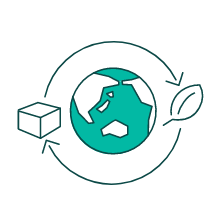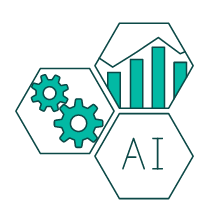2025年8月2日と3日に、「汐留サマースクール2025」が開催されました。これは、未来を担う世代の子どもたちが「好き」を見つけ、伸ばすことで、未来をワクワクしながら想像できるきっかけを作る「学び」のイベントです。TOPPANも2年連続で参加し、子どもたちに対してサステナブル視点で紙製飲料容器の魅力を伝える体験型のサステナビリティ教育を実施しました。今回はイベントを主催する日本テレビホールディングス株式会社R&Dラボの杉上佐智枝様をお招きし、TOPPAN企画担当の川田と共に、サステナビリティ教育における異業種連携の意義について対談しました。
昨年度から2倍超の来場者へ。関心度が高まり続ける学びの輪
「汐留サマースクール」開催の背景について教えてください。
 杉上様(日本テレビ): 他局ではテレビ局がある拠点で夏にイベントを実施するようなところもありますが、日本テレビはしばらく夏の自社開催イベントからは遠ざかっていました。そのような中で、本社がある汐留エリアで、主に小学生世代の親子を対象に記憶に残る学びと体験のイベントを実施できないだろうか、と考えて開催を決めたのが2023年です。こだわっている点は、必ずすべて無料で体験ができること。参加される企業に対しては販促につながる活動をお断りし、純粋に子どもたちへ学びの体験を提供するというポリシーに賛同していただいています。 初年度から「好きで未来作ろう」というスローガンを掲げ、子どもたちの「好き」を未来の夢につなげる体験を提供したいと考えていました。
杉上様(日本テレビ): 他局ではテレビ局がある拠点で夏にイベントを実施するようなところもありますが、日本テレビはしばらく夏の自社開催イベントからは遠ざかっていました。そのような中で、本社がある汐留エリアで、主に小学生世代の親子を対象に記憶に残る学びと体験のイベントを実施できないだろうか、と考えて開催を決めたのが2023年です。こだわっている点は、必ずすべて無料で体験ができること。参加される企業に対しては販促につながる活動をお断りし、純粋に子どもたちへ学びの体験を提供するというポリシーに賛同していただいています。 初年度から「好きで未来作ろう」というスローガンを掲げ、子どもたちの「好き」を未来の夢につなげる体験を提供したいと考えていました。
毎年8月に開催して3年目を迎え、スケールも大きくなっているようですね。
杉上様(日本テレビ): 今年は過去最多の37の共創パートナーが参加し、提供しているプログラムの数は40を超えました。 宇宙などの理科系プログラムから、アートや表現、サステナビリティにまつわるものまで幅広く集まっていただきました。初年度は約2万人だった来場者が、今年は参考値で4万3,000人に到達し、盛り上がりを実感しています。
TOPPANは昨年に続き2年連続の参加になりましたが、参加の経緯とサステナビリティ教育に取り組む背景を教えてください。
 川田(TOPPAN): TOPPANは「紙パック」のマークが付いた紙製飲料容器のリサイクルの重要性や資源循環を伝えることをテーマに、2年連続で参加しています。パッケージを通して分別やリサイクルの大切さを身近に感じてもらえるような機会を提供することを心掛けて企画しました。出展させていただいた経緯としては、脱炭素をテーマにした別のイベントに参画した際に、日本テレビさんも参加されていたんです。 そこでのご縁からお話しさせていただく中で、「汐留サマースクール」を紹介していただきました。TOPPANはBtoB企業なので生活者の皆さんと直接関わる機会があまりなく、私たちが取り組む資源循環やサステナビリティについて、生活者の皆さんに発信する貴重な機会だと思い、参加を決めました。
川田(TOPPAN): TOPPANは「紙パック」のマークが付いた紙製飲料容器のリサイクルの重要性や資源循環を伝えることをテーマに、2年連続で参加しています。パッケージを通して分別やリサイクルの大切さを身近に感じてもらえるような機会を提供することを心掛けて企画しました。出展させていただいた経緯としては、脱炭素をテーマにした別のイベントに参画した際に、日本テレビさんも参加されていたんです。 そこでのご縁からお話しさせていただく中で、「汐留サマースクール」を紹介していただきました。TOPPANはBtoB企業なので生活者の皆さんと直接関わる機会があまりなく、私たちが取り組む資源循環やサステナビリティについて、生活者の皆さんに発信する貴重な機会だと思い、参加を決めました。
学びと体験の両立が生む環境への気づき
体験授業の内容についても教えてください。
 川田(TOPPAN): 当日は「うちわペイント体験」と「クイズラリー」を実施しました。「うちわペイント体験」では、TOPPANの工場で紙製飲料容器の製造時に発生した端材を活用した再生手すき用紙で作ったうちわを用いて 、参加者の皆さんにデコレーションを行ってもらいました。「このうちわがパッケージをリサイクルしてできているの?」と目をキラキラと輝かせて驚く子どもたちの姿は、私たちにとっても大きな喜びでした。
川田(TOPPAN): 当日は「うちわペイント体験」と「クイズラリー」を実施しました。「うちわペイント体験」では、TOPPANの工場で紙製飲料容器の製造時に発生した端材を活用した再生手すき用紙で作ったうちわを用いて 、参加者の皆さんにデコレーションを行ってもらいました。「このうちわがパッケージをリサイクルしてできているの?」と目をキラキラと輝かせて驚く子どもたちの姿は、私たちにとっても大きな喜びでした。
昨年度は単独企業での参加でしたが、今年度は森永乳業様との共同出展でしたね。
川田(TOPPAN): TOPPANは飲料・食品や日用品など様々な企業の商品パッケージを企画・製造していますが、実は、一般向けに販売している自社の商材がほとんどないんですね。そうした中で、今年は弊社のカートカン®※などをご採用いただいている森永乳業さんと共同で参加させていただきました。 紙パックマーク付きの商品を交えてリサイクルの流れを伝えたことで、よりパッケージへの親近感を生み出すことができたと思っています。実際に「このマーク見たことある!」「いつも飲んでる商品の容器がリサイクルできるなんて知らなかった!」といった声がたくさんありました。
「うちわペイント体験」で実践した体験型授業の重要性や教育的価値について教えてください。
 川田(TOPPAN): プログラム全体としては、「学び」と「体験」の両立を大切にしています。例えば、パッケージリサイクルの現状などを紙芝居形式で楽しく学べるように工夫しました。紙パックマークの付いた容器が実際にどのくらいリサイクルされているかクイズ形式で考えてもらったり、実際の紙製飲料容器から「紙パックマーク」を見つけてもらったりと、小学校低学年のお子さんも多かったので、一方通行にならないような伝え方も心掛けています。
川田(TOPPAN): プログラム全体としては、「学び」と「体験」の両立を大切にしています。例えば、パッケージリサイクルの現状などを紙芝居形式で楽しく学べるように工夫しました。紙パックマークの付いた容器が実際にどのくらいリサイクルされているかクイズ形式で考えてもらったり、実際の紙製飲料容器から「紙パックマーク」を見つけてもらったりと、小学校低学年のお子さんも多かったので、一方通行にならないような伝え方も心掛けています。
参加者のリアクションはいかがでしたか?
川田(TOPPAN): このうちわは、一つひとつ手すきで作られており、パッケージをリサイクルした再生紙だからこその風合いが特徴です。再生紙に触れたお子さんの「ざらざらしている!」といった反応や、「これがさっきのパッケージからできているの ?」と学びを体感してもらえた瞬間は、とても嬉しかったです。 終了後のアンケートにも、「カートカン®と牛乳パックが仲間だと初めて知った」「パッケージのリサイクル率を知って驚いた」「分別しようと思う」などの感想がありました。こちらから資源循環の意義を押し付けるのではなく、なぜ?という好奇心を引き出して、考えてもらうきっかけにしたいなと思っています。今回は2日間だけのイベントでしたが、私生活でもリサイクルを思い出す体験になっていればいいな、と思います。
 杉上様(日本テレビ): “体験型教育”というのは「汐留サマースクール」全体で重視していることです。約330人収容の日テレホールで実施するステージイベントもあるのですが、2日間で6コンテンツ開催した中にも「ただ鑑賞するだけ」というものはひとつもなかったんですよね。例えば、私が携わった「ホワイトハンドコーラスライブ」は、難聴や弱視といった障害のある子もない子もみんなで音楽を表現するインクルーシブ合唱団で、参加者も手をたたいたり手歌の振り付けを覚えたりする、参加型のステージでした。ただ伝えて見せるだけではなく、みんなで体験し、一緒に楽しむことによって記憶に残る部分は多いと思います。
杉上様(日本テレビ): “体験型教育”というのは「汐留サマースクール」全体で重視していることです。約330人収容の日テレホールで実施するステージイベントもあるのですが、2日間で6コンテンツ開催した中にも「ただ鑑賞するだけ」というものはひとつもなかったんですよね。例えば、私が携わった「ホワイトハンドコーラスライブ」は、難聴や弱視といった障害のある子もない子もみんなで音楽を表現するインクルーシブ合唱団で、参加者も手をたたいたり手歌の振り付けを覚えたりする、参加型のステージでした。ただ伝えて見せるだけではなく、みんなで体験し、一緒に楽しむことによって記憶に残る部分は多いと思います。
メディア×パッケージ事業が描く未来
今回の日本テレビ様との連携は、従来のパッケージ製造におけるお客さま企業との関係とは異なる新しいパートナーシップだと思います。このような異業種連携がサステナビリティ推進において持つ意義や可能性について教えてください。
川田(TOPPAN): 日本テレビさんとTOPPANは一見共通点が少ないように見えるかもしれませんが、「サステナビリティ」という観点だと同じ立場として取り組めるのが面白いところだと思います。汐留サマースクールでの出会いから他の取り組みをご一緒した事例もあって、このイベントが異業種連携を生む場所にもなっているんですよね。
杉上様(日本テレビ): まさにそれは願っていることでもあり、イベントの2日間だけの関わりではなく、事前説明会やフィードバックの場を対面で実施することで協業や次回出展といった未来へつなげることができればいいなと考えています。
川田(TOPPAN): 杉上さんは「絵本専門士」という資格をお持ちで、読み聞かせ活動も行っていらっしゃいますが、身近なパッケージをテーマにリサイクルに関する絵本を一緒に作って読みかせをするといったコラボができたら面白そうだと思いました。見て聞いて触れて、五感を通してサステナビリティを学ぶ場を作れたらいいですよね。
杉上様(日本テレビ): すごくいいですね!TOPPANさんは素材のプロなので、絵本自体も斬新でエンターテインメント性のあるものができると思うんですよ。我々は情報発信は得意ですが、製品開発はできません。だからお互いのできることを持ち寄って子どもも大人もハッピーになることを実現したいですね。
様々な協業の可能性が見えてきそうですね。今後の展望もお聞かせください。
川田(TOPPAN): リサイクルなどのサステナブルな取り組みは、1社だけでは実現できないと思います。業界を問わず、様々な企業と連携していきたいですね。 サステナビリティ教育についても、1回のイベントではなく、やはり「継続」が重要だと思います。最近では、軟包装(フィルム)のリサイクルについても、学校やイベントで発信する機会が増えてきています。今後も生活者の皆さんの方との接点を持続的に生み出して、サステナビリティを体感する場を企画していきたいです。
杉上様(日本テレビ): 「汐留サマースクール」にとって、TOPPANさんのように強いポリシーを持って出展してくださる企業さんがいることはとても心強いです。私自身、日本テレビでサステナビリティ事務局も兼務していて、「うみスケと学ぶブルーカーボン」や「にじモと学ぶジェンダー」といったデジタルコンテンツをリリースするなど、絵本活動を通じて環境や人権問題に向き合うことが活動の軸となっています。今後、「汐留サマースクール」も地球の未来のことも考えていけるイベントにしていきたいという野望があるので、TOPPANさんのお力もお借りしつつ4年目以降も取り組んでいきます。
※カートカン®: TOPPANの提供する紙製飲料容器