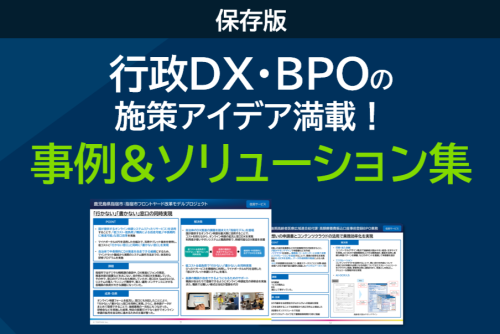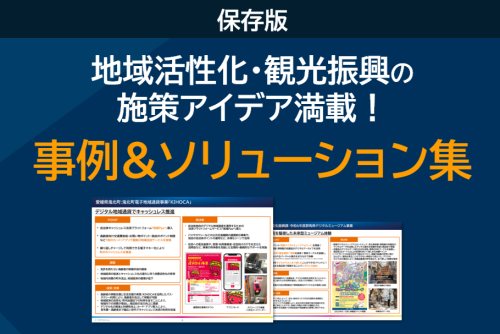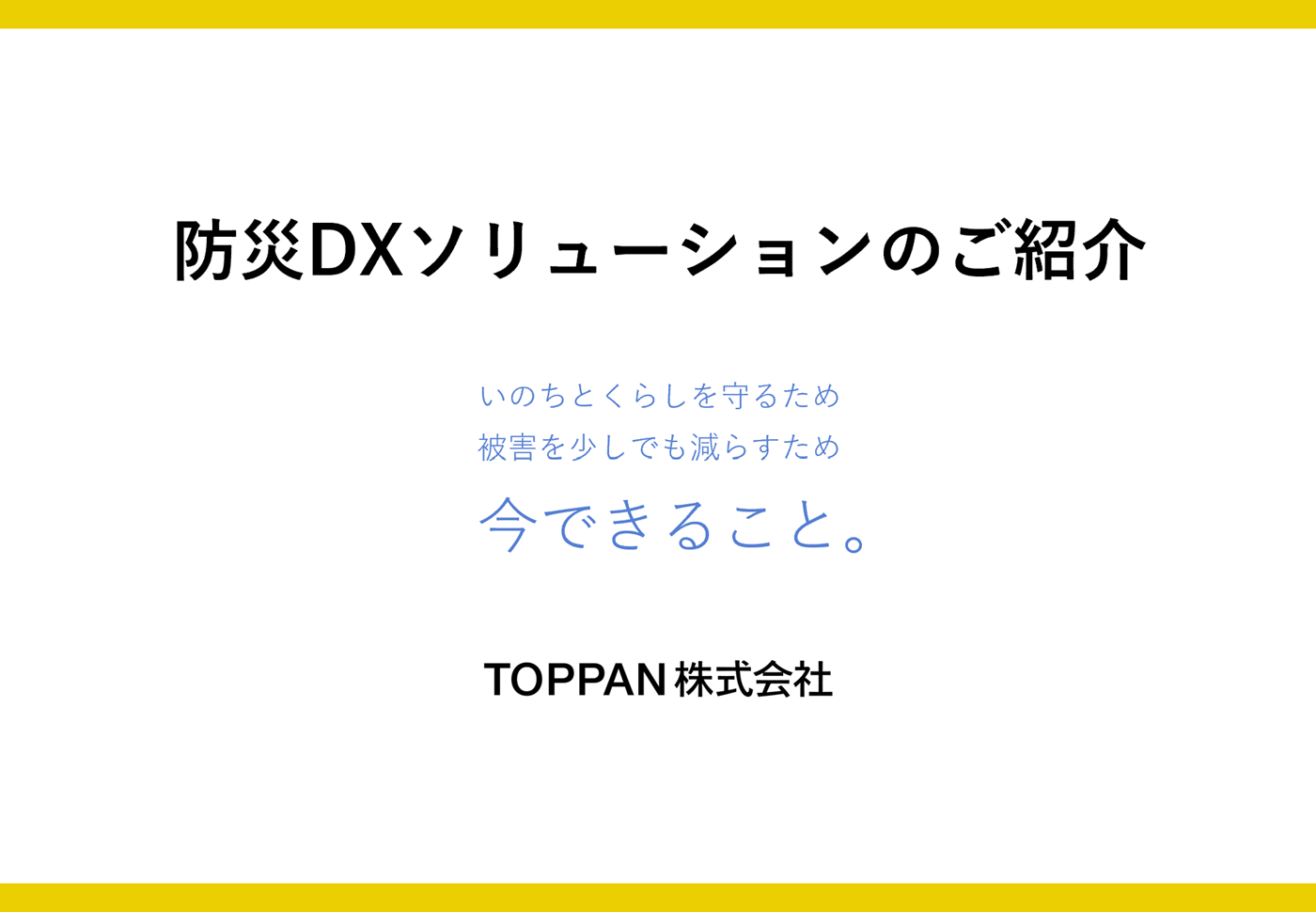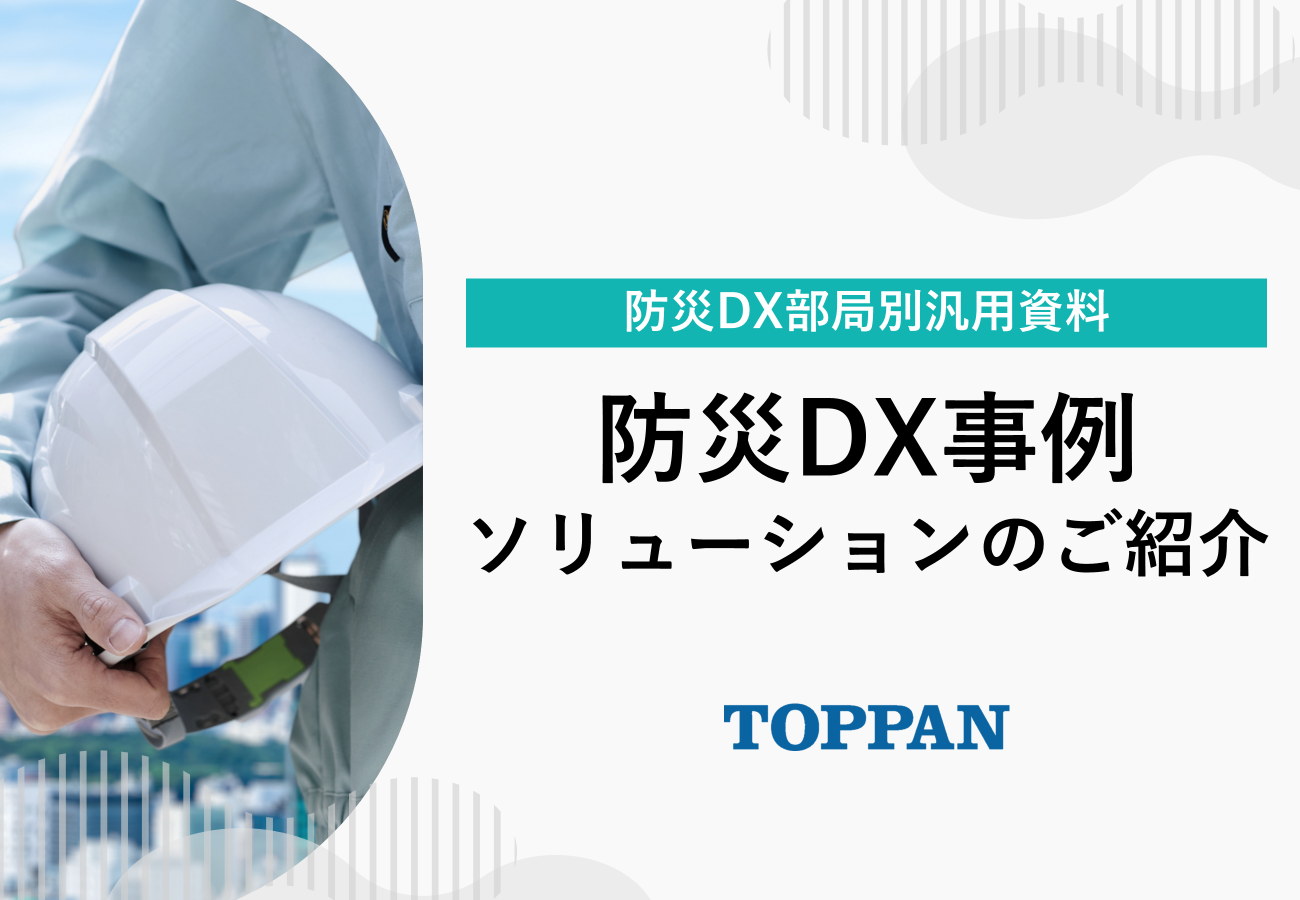2025.08.25
自治体における地震対策とは?
先進事例も紹介
地震による被害を最小限に抑えるためには、自治体による平時・地震発生時の包括的な地震対策が不可欠です。本記事では、自治体が取り組むべき地震対策と、参考となる先進的な事例をご紹介します。

近年、南海トラフ地震や首都直下地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震といった大規模地震の発生が懸念されるなかで、地域の安全を守るために自治体が果たす役割は、ますます重要になっています。地震による被害を最小限に抑えるためには、平時からの備えはもちろん、発災時の迅速な初動対応やその後の復旧体制の整備など、包括的な防災対策が必要不可欠です。
本記事では、自治体が取り組むべき地震対策について、平時から発災時までの基本的な考え方と、参考となる先進的な事例をご紹介します。
この記事でわかること
・自治体が取り組むべき平時・発災時の地震対策
・自治体が取り組んだ地震対策の事例
自治体が取り組むべき地震対策【平時】
地震はいつ起こるか予測が難しいため、備えとして平時から計画的に対策を講じることが重要です。自治体が取り組むべき地震対策として、以下が挙げられます。
●住民への啓発・訓練
●ハザードマップの作成・周知
●地域防災計画の作成・見直し
●インフラ・建築物の耐震強化
●備蓄の確保
●避難所・避難経路の整備
ここでは、これらの対策について詳しく解説します。
・自治体向け防災・減災支援サービス|TOPPAN SOCIAL INNOVATION
住民への啓発・訓練
地震への備えには、住民一人ひとりの防災意識と行動力の向上が欠かせません。防災講座やワークショップの開催は、住民の防災意識を高めるための有効な手段のひとつです。
また、高齢者や障がい者など配慮が必要な方々も含めた避難訓練を、定期的に実施することも重要です。これにより、実践的な対応力を養えるだけでなく、地域全体で助け合う体制づくりを進めることができます。
TOPPANでは、小中学生が楽しみながら学べるデジタル防災学習コンテンツや、リモートで体験できる防災アトラクションを提供し、子供たちの「自分ゴト」としての防災意識を育んでいます。
・デジタル防災教育・学習システム「デジ防災®」|TOPPAN BiZ
・リモート型防災アトラクション®~楽しみながらできる防災教育|TOPPAN BiZ
ハザードマップの作成・周知
地域の災害リスクを住民に正しく理解してもらうためには、自治体によるハザードマップの作成と普及が不可欠です。地震による被害想定に加え、津波や土砂災害、火災など複合的なリスク情報を含めることで、より実効性の高いマップとなります。
これらの情報は最新のデータに基づき定期的に更新し、防災講座や自治体広報などを活用して住民にわかりやすく発信しましょう。多言語対応や理解しやすい表記など、要配慮者や外国人住民への配慮も必要です。また、避難経路や避難所情報もあわせて提示することで、いざというときの迅速で適切な行動を後押しできます。
TOPPANが提供する「PosRe®」は、ハザードマップや避難所情報、気象データを一元管理し、ホームページやアプリで住民に共有できるため、防災情報の効果的な伝達に役立ちます。
・まちの情報集約・発信サービス「PosRe®(ポスレ)」|TOPPAN BiZ
地域防災計画の作成・見直し
地域防災計画とは、災害対策基本法に基づき自治体が策定する行動指針です。地域の地震リスクや特性を踏まえて作成し、社会情勢や科学的知見の変化に応じて、定期的に見直しを行うことが求められます。
また、地域防災計画を作成する際は、住民や専門家、関係機関の意見を取り入れ、実効性を向上させる訓練やシミュレーションを通じた検証も行いましょう。周知活動を通じて住民の理解と参加を促すことで、防災意識の向上につながります。
インフラ・建築物の耐震強化
地震による被害を最小限に抑えるために欠かせないのが、インフラや建築物の耐震性能の強化です。公共施設や学校、病院などの耐震診断を定期的に行い、必要に応じて補強・改修を進めることが求められます。
また、住宅の耐震化を促進するためには、住民向けの支援制度や補助金、相談窓口の整備も必要です。新たに建築される建物には、最新の耐震基準を適用し、安全性を確保しましょう。長期的な視点で、地域全体のインフラ整備を計画的に進めることが重要です。
備蓄の確保
災害発生時に迅速な対応を行うためには、食料や飲料水、医療品などの物資の備蓄が欠かせません。物資の種類や数量は避難所ごとに把握し、品質や使用期限も定期的に管理する必要があります。
また、家庭での備蓄の必要性を住民に伝えることも重要です。住民が自発的に備蓄を確保することで、地域全体の防災対応力を高められます。さらに、周辺自治体や地元企業と連携し、物資の融通体制を整備することで、災害時の支援体制の強化につながるでしょう。
避難所・避難経路の確保
地震発生時に備え、安全かつ円滑に避難できる環境を整備することも、平時に取り組むべき地震対策のひとつです。
具体的には、避難所の耐震対策や設備の整備に加え、避難経路の安全確保や誘導標識の設置を徹底する必要があります。また、バリアフリー対応を促進し、高齢者や障がい者などすべての住民が安心して避難できるような環境を整備することも重要です。
避難所の収容人数や備蓄状況は定期的に見直し、実態に即した整備を行うことが求められます。住民に避難所や避難経路の情報をわかりやすく伝え、避難訓練を通じて実践的な行動力を育成しましょう。
TOPPANの「避難所開設キット」は、災害時に求められる資材や手順を業務ごとにわかりやすく整理した一式で、避難所の迅速かつ的確な立ち上げと運営をサポートします。
自治体が取り組むべき地震対策【地震発生時】
地震が発生した直後には、迅速な対応が被害の拡大を防ぐ鍵となります。地震発生時に自治体に求められるのは、被害状況の把握と住民への情報提供、災害対策本部の設置、救助・救護活動、避難所の開設など、多岐にわたる対応です。
ここでは、地震発生時に自治体が取り組むべき具体的な対応と自治体が果たす役割について詳しく解説します。
被害状況の把握・住民への情報提供
地震発生直後は、正確な被害状況をいち早く把握することが、住民の安全確保と二次被害の防止につながります。住民からの通報や現地調査を効率的に行う体制を整え、得られた情報は関係機関と迅速に共有しましょう。
同時に、住民の不安の軽減を図るため、適切でわかりやすい情報を迅速に提供することも欠かせません。SNSやWebサイト、メール配信など複数の手段を活用して発信するほか、誤情報の拡散を防ぐ仕組みも必要です。
TOPPANの「あんしんライト」は、要支援者を含めた幅広い住民に確実な情報伝達を行うための有効な手段として活用できます。
・自治体向け住民見守りサービス「あんしんライト」|TOPPAN BiZ
災害対策本部の設置
地震発生後における自治体の対応を統括するのが「災害対策本部」です。災害対策本部の設置により、指揮命令系統が明確になり、関係部署や外部機関との連携を図りやすくなります。避難所運営や救援活動の調整、住民への支援活動など、あらゆる災害対応の統括役を担う重要な拠点です。
また、災害対策本部は24時間体制での運用が求められます。人的・物的な備えと、マニュアルの整備により継続的な対応を維持しましょう。
救助・救護活動
地震発生直後は、人命を守るための救助活動が最優先事項です。負傷者の救護や医療機関への搬送を速やかに行うとともに、警察・消防・医療機関と連携して救助体制を強化しましょう。
また、孤立地域や高齢者・障がい者といった要配慮者への支援にも重点的に対応する必要があります。避難所では応急医療や日常生活のサポートを提供し、物資や人員の不足に備えて、近隣自治体や支援団体との協力体制を事前に整えておくことも重要です。
被災者の受け入れ・生活支援(避難所の開設)
地震発生後は、自宅に住めなくなった住民を受け入れるために、避難所を迅速に開設し、安全で快適な生活環境を確保することが求められます。衛生管理や感染症対策を徹底し、食料・水・生活必需品を適切に供給できる体制を整えることが不可欠です。
また、高齢者や障がい者、乳幼児連れなど要配慮者向けの専用スペースや支援体制を整え、すべての避難者が安心して過ごせる環境を整える必要があります。
さらに、避難生活に伴う心理的負担に配慮し、相談窓口やメンタルケアの体制づくりも忘れてはなりません。避難所運営の混乱を避けるためには、事前のスタッフ教育と業務マニュアルの整備が効果的です。
TOPPANの「避難所開設キット」は、避難所運営に必要な業務をタスクごとに整理しており、混乱しやすい災害時の現場でも円滑な運営を可能にします。
自治体による地震対策の事例
全国の自治体では、地震による被害を最小限に抑えるため、住民の防災意識を高める多様な取り組みを実施しています。特に近年注目されているのは、最新のデジタル技術を活用した新たな防災教育の推進です。
また、防災訓練や避難行動のシミュレーションを通じて、実践的な対応力を育成する活動も展開されています。ここでは、TOPPANが支援した、先進的な地震対策を実践している自治体の取り組み事例をご紹介します。
【三重県】デジタルコンテンツによる防災学習支援
南海トラフ地震や津波などの自然災害への備えとして、三重県が進めているのは、児童生徒の防災教育を強化する取り組みです。新型コロナウイルスの影響で体験型防災学習の実施が難しくなったことを受け、デジタルコンテンツを活用した新たな防災学習支援を展開しています。
具体的には、家庭で保護者と一緒に学べる教材や、学校で活用できる授業用資料、教室や通学路など5つの場面を想定した避難行動動画、年齢に応じた学習コンテンツなどです。教員の授業運営もサポートし、学校と家庭の連携を通じて、子供たちの防災力を育んでいます。

・参考:防災学習を支えるデジタルコンテンツの提供および教育支援の実施|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION
【徳島県牟岐町】防災意識の向上に寄与する災害体験VRによる「リアルな被災疑似体験」
南海トラフ地震や津波のリスクを抱える徳島県牟岐町では、住民の防災意識向上が大きな課題となっていました。そこで導入されたのが、実際に災害を体験しているような感覚で学べる、VR(仮想現実)を用いた「被災疑似体験」です。
防災分野の専門家監修のもと、牟岐町オリジナルのシナリオを制作し、地震発生時の対応を体験的に学べる内容となっています。また、小中学生向けには、タブレットやパソコンを活用して段階的に防災知識を習得できるデジタル防災学習システム「デジ防災®」を導入しました。幅広い世代に向けて、実践的で継続性のある防災教育を提供しています。
・住民の防災意識を高めるためには?災害体験VR制作事例|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION
【香川県三豊市】防災意識の自分ゴト化を支援するデジタル防災教材

香川県三豊市では、激甚化・頻発化する自然災害への備えとして、防災教育のさらなる充実が求められていました。特に、コロナ禍により従来の避難訓練が制限されたことで懸念されていたのが、防災教育の地域差や実践力の低下です。
こうした状況を踏まえ、三豊市では全国に先駆けて、小中学生向けのデジタル防災学習システム「デジ防災®」を導入しています。専門家が監修した全80のコンテンツを通じて、防災知識を段階的に学べる仕組みを整備しました。
これにより、知識の習得と習熟度が可視化できるようになり、防災計画の見直しや知識の偏り解消に役立っています。また、教職員の負担軽減や学習機会の平等化により、より実効性のある防災教育を実現しました。
・参考:小中学生向けのデジタル防災教材を導入|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION
【香川県善通寺市】住民の安心・安全を確保する戸別送受信機の導入
香川県善通寺市では、防災無線が届きにくい地域や状況下での情報伝達が課題となっていました。特に、高齢者や要支援者への支援が急務とされるなか、善通寺市が導入したのが、戸別送受信機「あんしんライト」です。土砂災害警戒区域内に住む避難行動要支援者のいる世帯を対象に、自治体職員が各戸を訪問し、機器の設置や使用方法の説明を行うことで、スムーズな導入を実現しました。
「あんしんライト」は、LEDの光と音声によって、緊急時に迅速な避難を促します。また、平時には双方向通信機能により、各端末の利用状況・状態の可視化が可能です。クラウド上で稼働状況を把握できる体制を整えることで、住民の安心・安全な暮らしを支えています。
・参考:住民の安心・安全と見守りを支援|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION
・自治体向け住民見守りサービス「あんしんライト」|TOPPAN BiZ
【大阪府吹田市】防災知識の普及・啓発による地域防災力の向上

大阪府吹田市では、地域全体の防災力を底上げするために、市民一人ひとりの防災・減災意識の向上が課題となっていました。その対策として実施されたのが、防災ブックとハザードマップの全戸・全事業所への配布です。これらは多言語や点字にも対応し、誰もが理解しやすい内容で制作されています。
また、防災イベントを開催し、地震や風水害を体感できるアトラクションを通じて、参加者が楽しみながら防災行動を学べる機会も提供しました。さらに、電子チラシサービス「Shufoo!」を活用したプッシュ通知により、防災情報の周知徹底も行っています。
こうした多面的な取り組みにより、防災に関心が薄い層にも働きかけ、市民全体の意識向上が図られています。
・参考:すべての住民の防災・減災意識を向上させる|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION
【岩手県】被災地域の経験・教訓を未来につなげるデジタルアーカイブの構築

東日本大震災からの復興が進む一方で、震災の記録や教訓の風化、資料の散逸が懸念されています。岩手県ではこうした課題に対し、被災地域の記録を集約・デジタル化し、Web上で公開する「デジタルアーカイブ」を構築しました。
誰もがアクセスできる仕組みを整備したことにより、学校教育や防災・減災研究、地域内外の交流促進など、多目的に活用されています。この取り組みは、震災の教訓を次世代へ伝える手段として、防災力の強化に大きく貢献しています。
・参考:貴重な被災地域の記録を収集し、経験・教訓を後世に残す|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION
地域の安全を守る力を育むために、地震対策に取り組もう
いつ起こるかわからない地震に備えるためには、自治体による計画的な対策が必要です。防災教育の推進や住民への情報発信、避難所やインフラの整備など、平時からの備えが被害を最小限に抑えるための基盤となります。
また、地震発生時には被害状況の把握や迅速な救助・救護、避難所運営など、多角的かつ即応的な対応が求められます。
過去の災害経験や最新のデジタル技術を活用した事例から学び、地域防災力を高めていくことは、地域の防災体制の強化に役立つでしょう。自治体と住民が協力しながら、防災への取り組みを日常のなかに根付かせていくことが重要です。
TOPPANでは、自治体における地震対策を多方面から支援するサービスを提供しています。地震対策の進め方にお悩みの際は、ぜひご相談ください。

参考文献
- 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会第5回会合 https://www.bousai.go.jp/kaigirep/chousakai/tohokukyokun/5/pdf/sub2.pdf
- 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223/