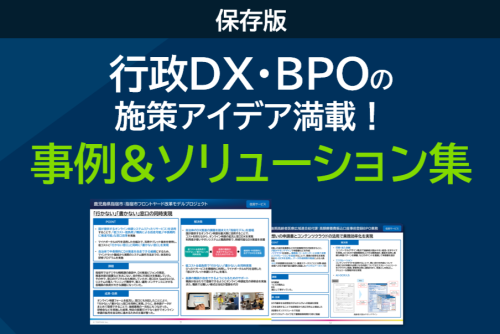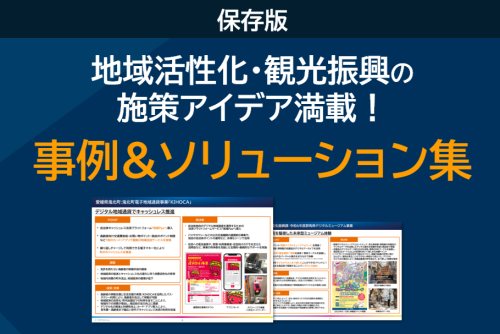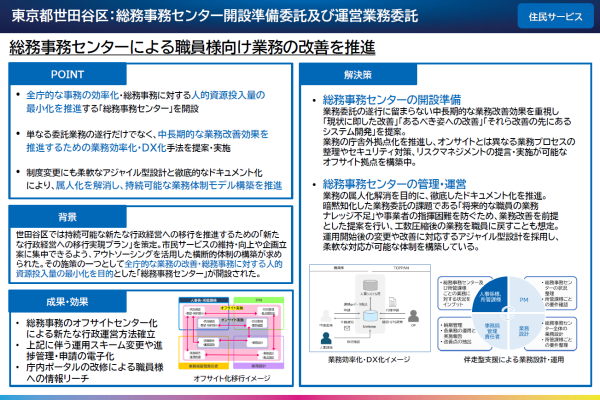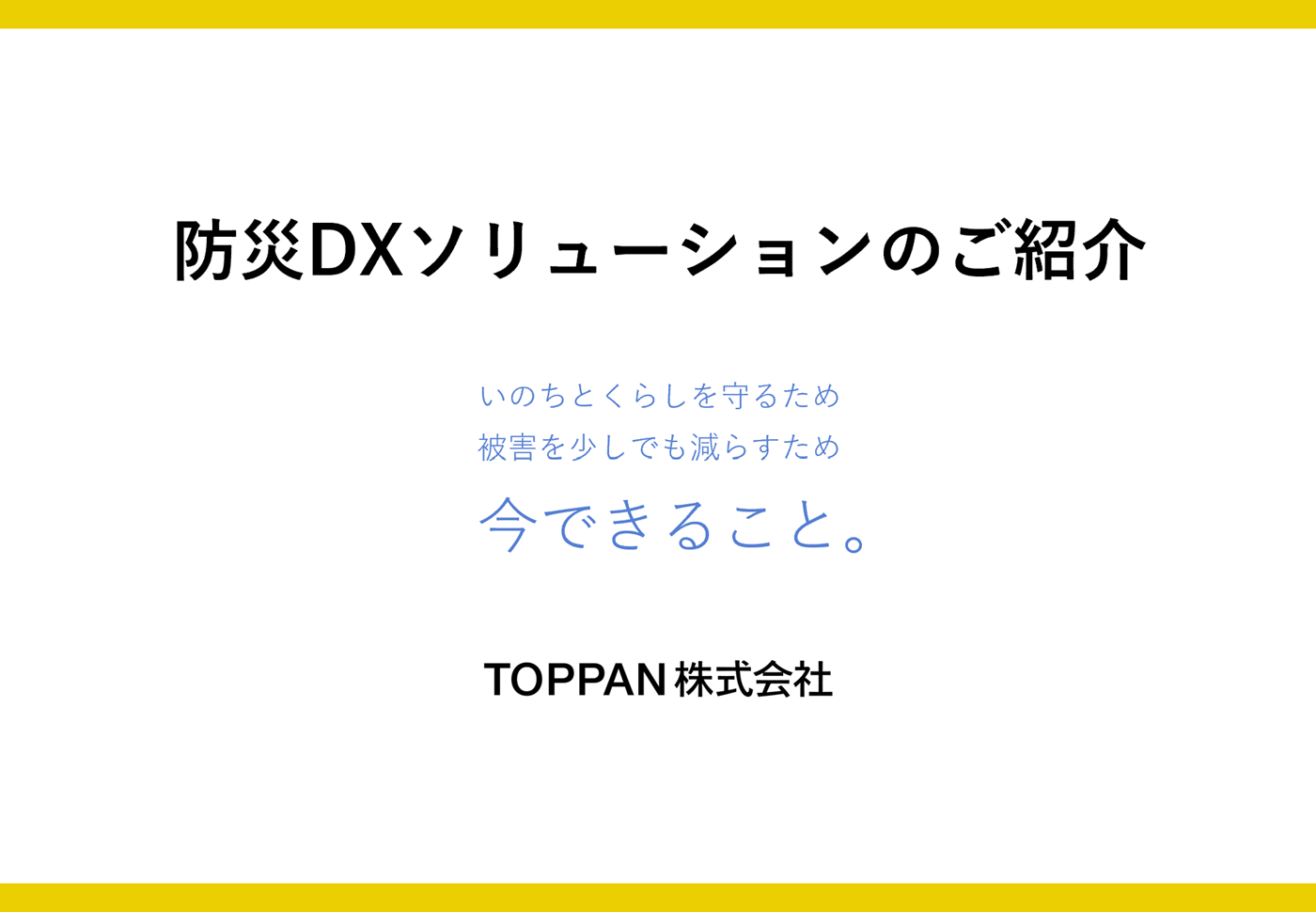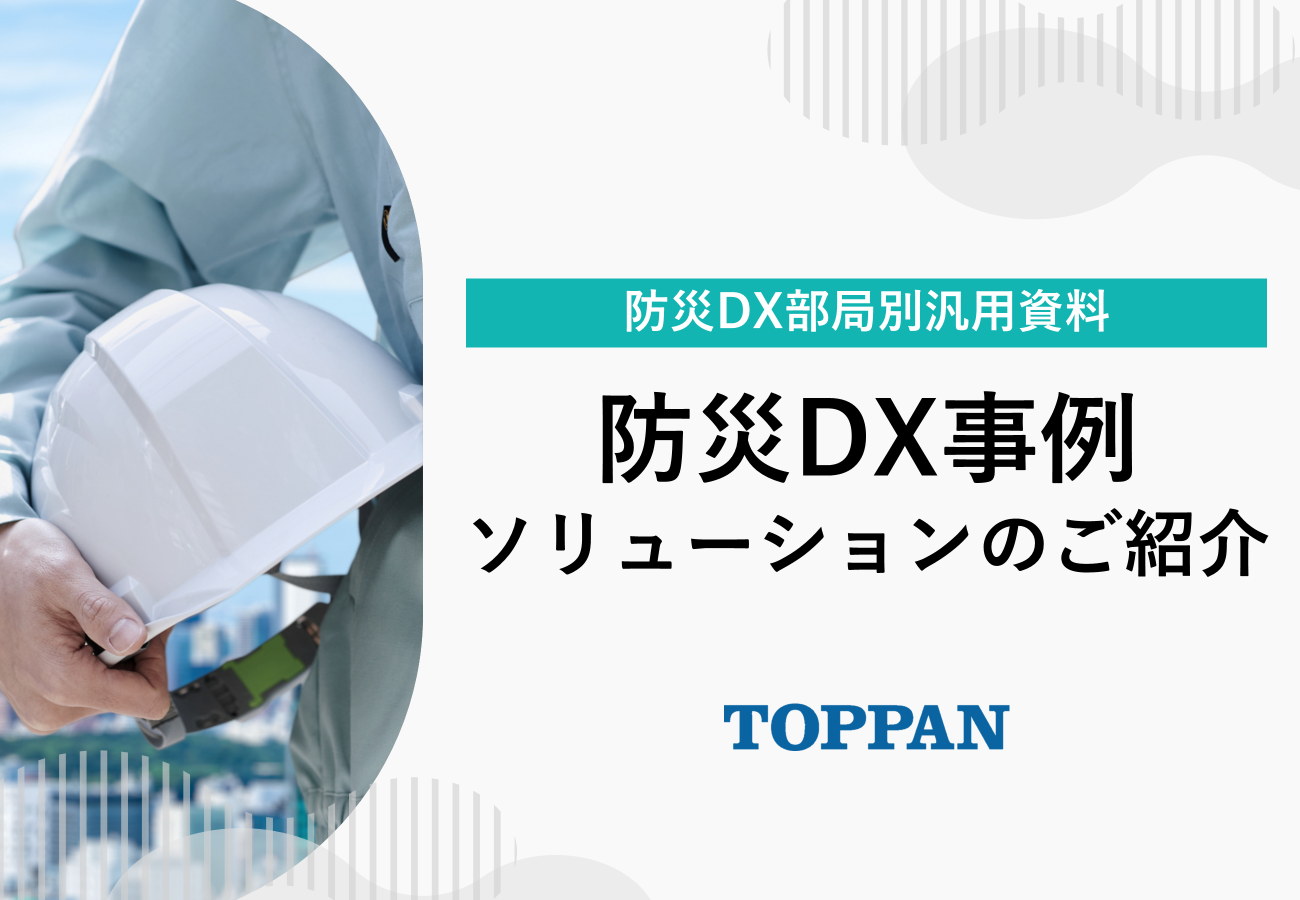2025.10.21
減災とは?自治体が支援する減災対策を解説
地震や豪雨などの自然災害への備えとして、被害を防ぐ「防災」だけでなく、被害を抑える「減災」の視点も重要です。本記事では、減災の意味や必要性、自治体や住民が実践できる対策、具体的な事例をご紹介します。

地震や豪雨などの自然災害が多発する日本では、被害を未然に防ぐ「防災」だけでなく、被害を最小限に抑える「減災」の考え方も重要です。減災は、自治体が主導する施策と、住民一人ひとりの取り組みが連携することで、より大きな効果を発揮します。
この記事では、減災の意味や必要性を解説するとともに、自治体や住民が実践できる具体的な減災対策、自治体の取り組み事例をご紹介します。
この記事で分かること
・減災の重要性
・自治体と住民が取り組むべき減災対策
・他自治体における成功事例
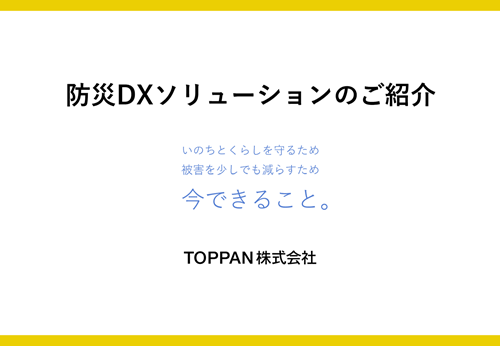
減災とは
減災とは、災害による被害を「完全に防ぐことは難しくても、できる限り抑える」ための取り組みを指す概念です。防災が「被害を未然に防ぐ」ことを目的とするのに対し、減災は「被害を最小限にとどめる」ことを重視する点が特徴です。
自治体は地域の特性に応じた施策を進め、住民の生命と生活を守る役割を担います。その際には、インフラ整備などのハード面と、防災教育や避難体制づくりといったソフト面の両面で対策することが重要です。
また、効果的な減災を実現するためには、自治体による支援(公助)に加え、住民自身の備え(自助)や地域での助け合い(共助)が不可欠です。
減災の重要性
自然災害を完全に防ぐことは難しいため、被害をできる限り抑える「減災」の考え方は極めて重要です。人的被害や経済的損失を最小限に抑えることで、地域社会の早期復旧・復興を可能にします。また、災害リスクを正しく理解し、事前に対応策を講じることで、住民の安心感や行動力を高めることにもつながるでしょう。
さらに、災害に強いインフラの整備や避難計画の策定は、平常時の生活の質を向上させる取り組みでもあります。自治体による減災対策は、持続可能で強靱なまちづくりに欠かせない重要な施策のひとつといえるでしょう。2025年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太方針2025)」でも、国土強靱化が基本方針のひとつとして示されています。
自治体が取り組むべき減災対策
自治体は「公助」として地域の安全を守る重要な役割を担っており、多角的で実効性のある減災対策を計画的に進める必要があります。具体的には以下の取り組みが挙げられます。
●危機意識の浸透:ハザードマップの整備やリスク情報の可視化を通じて、住民に災害リスクを理解してもらう
●避難・受け入れ体制の強化:避難所、防災拠点、福祉避難所の確保による災害時の受け入れ体制の整備
●防災教育・訓練の実施:地域住民への教育や訓練を通じて、自助・共助の促進と防災意識の定着
●地域連携の推進:民間企業や他自治体との連携、防災協定の締結による地域全体での仕組みづくり
●災害後を見据えた体制整備:BCP(事業継続計画)や復旧支援体制の構築
自治体がこれらの減災対策を行うことで、住民の安全を守り、災害時の被害を最小限に抑えることが可能です。
住民が取り組むべき「7つの備え」と自治体ができる支援
内閣府では、住民一人ひとりが実践すべき減災行動として「7つの備え」を提唱しています。平常時から少しずつ備えや工夫を心掛けることで、災害時の被害の軽減につながるでしょう。
ここでは、住民が取り組むべき「7つの備え」の具体的な内容と、自治体ができる支援についてご紹介します。
1. 自助と共助
災害時にもっとも重要なのは、自分と家族の命を守る「自助」です。同時に、地域住民と助け合う「共助」も被害を最小限に抑えるうえで欠かせません。
特に発災直後の初動対応では、公的支援(公助)がすぐに届かないことが多く、自助と共助の力が減災の成否を左右します。
自治体には、このような自助・共助の重要性を伝える広報や防災教育、防災訓練の実施を通じて住民の意識向上を支援することが求められます。町内会や自主防災組織の活動の支援を通じて、共助体制の強化を後押しすることも重要です。
TOPPANでは、自然災害を疑似体験できるVRコンテンツを提供し、災害を「自分ごと」として捉えられるようにすることで、防災・減災に向けた行動意識の情勢を支援しています。
・災害体験VR|地震・津波・自然災害をVRで体験|TOPPAN Biz
2. 地域の防災マップを確認する
防災マップは、洪水・土砂災害・津波などの災害リスクや避難所の場所を視覚的に示す重要なツールです。地域の災害リスク(洪水、土砂災害、津波など)を事前に把握しておくことで、いざという時の迅速な避難行動につながり、被害の軽減に役立ちます。
自治体の取り組みとしては、マップの作成・更新・配布のほか、WEB公開や多言語対応など、誰もがアクセスしやすい環境を整備することが挙げられます。また、地域説明会や学校・地域団体を通じた周知活動も、住民の理解を深めるうえで効果的です。
TOPPANの「PosRe®(ポスレ)」は、地域情報の収集・管理・発信を効率的に行えるプラットフォームです。自治体HPやアプリを通じて、住民へ必要な情報をワンストップで届けることが可能です。
・まちの情報集約・発信サービス「PosRe®(ポスレ)」|TOPPAN Biz
3. 地震に強い家づくり
住宅の耐震性を高めることは、自身と家族の命を守る「自助」の一環です。特に古い住宅の場合、耐震診断を受け、必要に応じて補強工事を行うことが重要です。また、家具の転倒防止やガラスへの飛散防止フィルムの貼付など、室内の安全対策も欠かせません。
自治体では、耐震診断や補強工事への補助制度を整備し、住民の負担を軽減する支援を行う必要があります。また、地域の地盤特性や過去の被害状況を踏まえた情報提供を行うことで、安全な住まいづくりを後押しできます。
4. 災害に対する正しい知識
災害時に適切な行動を取るためには、平常時から正しい知識を身につけておくことが不可欠です。家具の固定や非常用品の備蓄、避難時の注意点など、実践的な知識を習得しておくことが減災につながります。また、ハザードマップや自治体ホームページを通じて、地域特有のリスクを把握することも大切です。
自治体では、防災講座や広報誌、防災アプリなどを活用し、さまざまな手段で住民へ情報提供を行うことが求められます。また、住民が誤情報や思い込みに惑わされないよう、信頼できる公的情報を定期的に確認する習慣を身につけてもらうことも重要です。
TOPPANは、リモート参加型の防災アトラクションや、小中学生向けのデジタル学習コンテンツを提供し、楽しみながら正しい知識を学ぶ機会を創出しています。
・リモート型防災アトラクション®~楽しみながらできる防災教育|TOPPAN Biz
・小中学生への学校での防災教育に、楽しく学べる防災教育・学習システム「デジ防災」|TOPPAN Biz
5. 日ごろの備え
災害時に落ち着いて行動するためには、日ごろの備えが欠かせません。家庭では、飲料水・非常食・携帯トイレ・常備薬・懐中電灯などを、最低3日分以上備蓄しておくことが推奨されています。また、非常用持ち出し袋の中身も、家族構成や健康状態に合わせて定期的に点検・更新することが大切です。
自治体では、備蓄リストや点検ポイントをパンフレットやホームページで発信することや、備蓄品購入への助成制度や啓発キャンペーンの実施など、さまざまな支援を行う必要があります。
住民に向けた啓発活動とあわせて、職員や来庁者向けの備品の準備も重要です。TOPPANでは、必要な物資を効率的にまとめて保管できる災害用備蓄スタンドを提供し、安心できる備えをサポートしています。
・災害用備蓄スタンドで災害備蓄品をコンパクトにオールインワン|BISTA/ビスタ|TOPPAN Biz
また、火災などの人為災害を発生させないための備えも必要です。特に、地震火災を防ぐには、感震ブレーカーを設置する、ストーブ等の近くに可燃物を置かないといった事前の対策が欠かせません。
近年は、スマートフォンやモバイルバッテリーに使われているリチウムイオン電池による火災も増えてきました。TOPPANでは、火災発生時の熱に反応して消火できる「FSfilm®」なども開発しています。
・優れた初期消火効果を持つ消火フィルム「FSfilm®」を開発
6. 家族で避難・安否確認の方法を決めておく
災害発生時には家族が離ればなれになる可能性があるため、事前に避難先や連絡手段を決めておくことが重要です。集合場所や避難ルート、避難所の場所を家族全員で共有することで、安心感が高まります。
また、災害用伝言ダイヤル(171)やSNS、安否確認アプリなど、複数の連絡手段を用意しておくことも有効です。
自治体が行う減災の取り組みには、情報の提供や防災ガイドブックの配布を通じ、家庭での話し合いを促すことなどが挙げられます。さらに、避難訓練や学校・地域との連携により、子どもや高齢者の安否確認体制の構築も進めることが望ましいでしょう。
7. 地域とのつながり
災害時には、近隣住民との助け合い(共助)が避難や安否確認、初期対応において大きな力となります。そのため、日ごろから地域行事や防災訓練に参加し、顔の見える関係を築いておくことが重要です。これは、高齢者や障がい者など、支援を必要とする人への配慮や協力体制の構築にもつながります。
自治体には、町内会や自主防災組織の活動支援、防災訓練の実施、地域交流の場の提供などにより、こうしたつながりづくりを後押しすることが求められます。防災を契機としたネットワーク形成は、平時の防犯や見守り活動にも好影響を与える取り組みといえるでしょう。
自治体による減災の取り組み事例
各自治体では、地域の特性や課題に応じた多様な減災対策が実践されています。ICTや情報発信を活用した減災施策により、さまざまな世代や属性に対応した防災教育や啓発活動を展開することで、住民の防災意識向上と安心・安全の確保を図ることが可能です。
ここでは、TOPPANがご支援した、自治体による減災の取り組み事例をご紹介します。
【三重県】児童生徒の防災教育を支援するデジタルコンテンツの提供

南海トラフ地震や台風などに備え、児童生徒の「自助」力を育む防災教育が求められています。しかし、コロナ禍によって体験型学習や家庭との連携が難しくなったことで、防災教育の継続に課題が生じていました。この課題に対応するために三重県が取り組んだのが、場所や状況にとらわれず学べるデジタルコンテンツの開発です。
教室・運動場・通学路など、5つの場面における地震時の行動を学ぶ動画を制作し、動画視聴後に自分の行動を考えるワークを実践してもらうことで、判断力を養う仕組みです。また、年齢別教材や家庭・教員向けの活用支援も行っており、学校と家庭の連携を促進しています。
・ 参考:防災学習を支えるデジタルコンテンツの提供および教育支援の実施|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION
【三豊市】防災意識の自分ゴト化を支援するデジタル防災教材の導入

激甚化・頻発化する自然災害に備え、学校現場での防災教育の拡充も課題となっています。
このような状況の中、香川県三豊市では、全国初となるデジタル防災教材「デジ防災®」を三豊市の小中学校に導入。コロナ禍や多忙なカリキュラムの中でも、効果的かつ継続的に学べる仕組みを整備しました。
専門家監修の全80コンテンツを活用することで、児童・生徒はクイズ形式で楽しみながら防災知識を習得できます。また、学習の習熟度を可視化することで、学校や地域ごとの防災力を把握・強化する仕組みづくりにも貢献しています。
ブラウザベースで端末を問わず利用できるため、教職員の授業準備の負担軽減も可能です。児童・生徒が防災を自分ごととして意識できるようにし、地域全体の防災教育の底上げを実現した取り組みといえるでしょう。
・参考:小中学生向けのデジタル防災教材を導入|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION
・参考:小中学生への学校での防災教育に、楽しく学べる防災教育・学習システム「デジ防災」|TOPPAN Biz
【牟岐町】防災意識の向上に寄与する災害体験VR

南海トラフ巨大地震による津波被害が懸念される徳島県牟岐町では、住民の防災意識向上が重要な課題となっています。この課題に対応するため、VRを活用して「リアルな災害の疑似体験」を提供し、防災を自分ごととして捉えてもらう取り組みを実施しました。
具体的には、防災研究者の監修のもと、津波や地震の発生から対応までを体感できるオリジナル災害体験VRを制作。体験後に、地震の仕組みや避難行動の解説を行うことで、防災知識の定着を図っています。
さらに、小中学生向けに段階的に防災知識を学べるデジタル学習システム「デジ防災®」も導入し、住民全体の防災意識醸成と次世代への教育強化を実現しています。
・参考:住民の防災意識を高めるためには?災害体験VR制作事例|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION
・参考:防災意識向上を、リアルな体感経験で「災害体験VR」|TOPPAN Biz
【東京包装容器リサイクル協同組合】リチウムイオン電池の発火リスクを低減させる減災・防災の取り組み

モバイルバッテリーをはじめとする小型電子機器に含まれるリチウムイオン電池は、強い圧力や衝撃によって発火する特性があり、全国で火災事故の原因となっています。東京都新宿区の東京包装容器リサイクル協同組合では、回収した電池の発火事故を防ぐため、回収ボックスにTOPPANが開発した「FSfilm®」を導入しました。
「FSfilm®」は、火災発生時の熱に反応して、消火効果のあるエアロゾル(微細な粒子)を放出することで、素早く延焼拡大を防げる特殊なフィルムです。紙素材で省スペース、かつ消火時に有害なガスが発生することもないため、さまざまな用途で安全に使用できます。
新宿区では「FSfilm®」の導入とあわせて、回収手順の整備や、住民向けの啓発活動も展開することで、安全に小型電池の回収ができる地域モデルを構築しました。
・参考:リチウムイオン電池回収時の「発火リスク」に備え、防災対策と環境配慮の両立を実現|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION
【吹田市】住民の防災・減災意識の向上を促す啓発活動
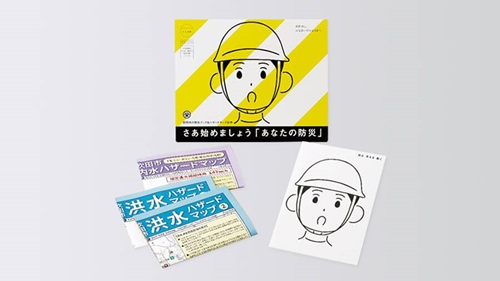
大阪府吹田市では、在留外国人や障がい者など多様な住民への防災啓発が課題となっていました。そこで、防災意識があまり高くない市民にも働きかける手段として、防災ブックとハザードマップを全戸・全事業所へ配布しました。
防災ブックは、日本語・英語・中国語・韓国語のほか、点字版にも対応しており、クイズやイラストを交えることで、幅広い世代が理解しやすい仕様です。
また、体感型アトラクションによる防災イベントを開催し、楽しみながら学ぶ機会も提供しています。電子チラシサービス「Shufoo!」を活用したプッシュ通知で、情報を効果的に周知しています。
・参考:すべての住民の防災・減災意識を向上させる|事例紹介|TOPPAN SOCIAL INNOVATION

不測の事態に備えるために、減災への取り組みを始めよう
自然災害は発生の予測が難しく、完全に防ぐことはできないため、被害を可能な限り小さく抑える「減災対策」が不可欠です。自治体と住民が連携し、自助・共助・公助のバランスを意識して対策を進めることが大切です。
さらに、防災教育やデジタル技術など多様な手法を組み合わせることで、備えをより強固なものにできます。
TOPPANでは、自治体向けに幅広い減災支援サービスを提供しています。具体的な進め方にお悩みの際は、ぜひ一度ご相談ください。

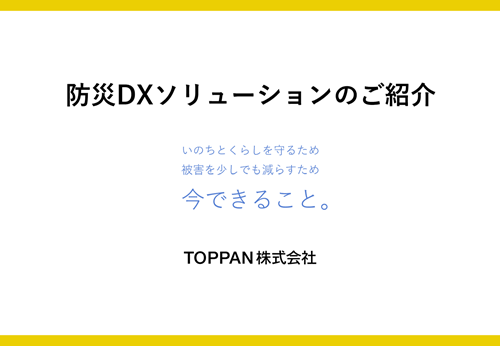
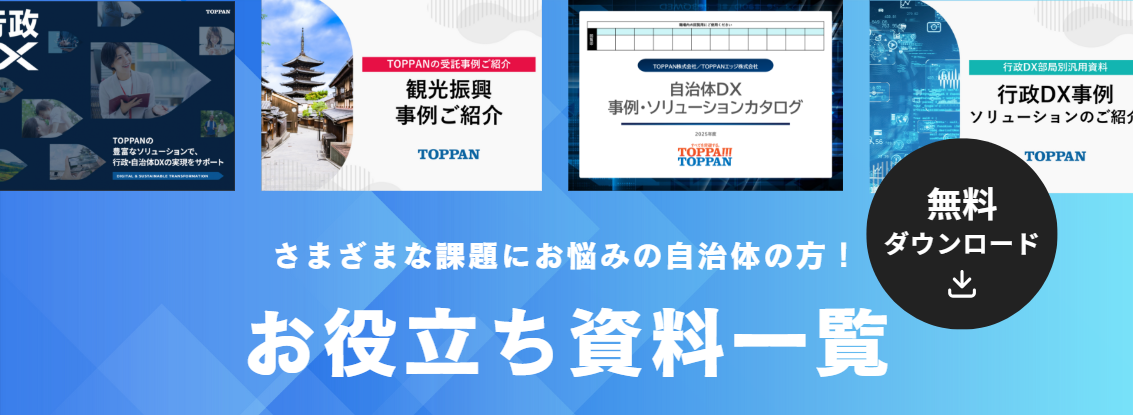
参考文献
- 内閣府 減災のてびき(減災啓発ツール)(https://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen/gensai/tebiki.html)
- みやぎ地域防災のアイディア集(https://www.pref.miyagi.jp/documents/8132/841830.pdf)
- 総務省 令和2年版 消防白書(https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r2/chapter1/section1/para3/56542.html)
最新コラム
関連コラム
関連ソリューション
関連事例
-

三重県
防災学習を支えるデジタルコンテンツの提供および教育支援の実施
地震発生時の避難行動を学ぶ動画および児童生徒用の防災学習デジタルコンテンツの作成
-

宮城県 仙台市
VR技術を用いたリアリティのある360度映像の災害体験コンテンツにより被災疑似体験をDXで実現し、市民の防災・減災意識向上
仙台市の津波・水害等 災害疑似体験VR動画制作業務 住民の防災意識を高めるためのオリジナル災害体験VRコンテンツ制作
-
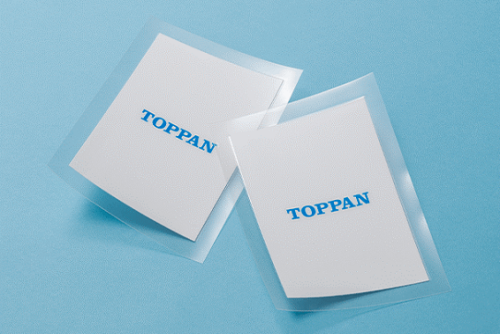
新宿区
リチウムイオン電池回収時の「発火リスク」に備え、
防災対策と環境配慮の両立を実現初期消火効果を持つ特殊フィルム「FSfilm®」導入。使用済み小型電池回収時の発火リスクを低減と回収現場の安全性向上を両立させた、防災・減災の取り組み事例